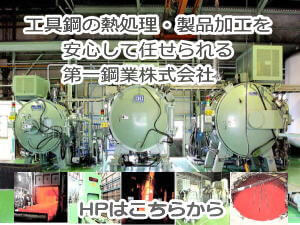熱処理記事の一覧
1 SUS304の脱磁
オーステナイト系ステンレスのSUS304で、磁気を帯びてしまって、困ることがありますね。根本的でうまい解決法はないのが現状ですが、脱磁などについて、参考になりそうなことを紹介しています。
→このページへ
2 SUS440Cの焼入れ硬さ
マルテンサイト系のSUS440Cは、硬い硬さの出るステンレス鋼ですので、SKD11などのように60HRC程度の硬さがほしいのですが、57HRC程度しか出ないことがよくあります。この鋼種についての説明をしています。
→このページへ
3 超サブゼロについて
0℃以下に冷やす処理をサブゼロ処理といいますが、特に-100℃以下にする処理を超サブゼロ処理・クライオ処理などと呼ばれます。
超サブゼロ処理で、耐摩耗性が増す、寿命が伸びる・・・などの効果があるとされていますが、あまり良くわかっていません。その他の話題を含めて熱処理関連の超サブゼロ処理について紹介しています。
→このページへ
4 熱処理における加熱時の保持時間について
焼入れや焼戻しにおける保持時間についての話題や考え方を紹介しています。
熱処理を仕事にする人向きの話題かもしれませんが、興味があれば、次の焼戻し回数の問題とあわせてお読みください。
→このページへ
5 工具鋼の焼戻し回数は何回が適当なのか
工具鋼の焼戻しは何回するのがいいのかについて、一般には誤解される説明も多いようです。
業界の方でも、勝手な考え方がまかり通っているようなのですが、教科書では載っていない、作業上の問題を含めて、その考え方を説明しています。
→このページへ
6 工具鋼のワイヤカット時の注意点や対策
焼入れした金型などの硬い品物でも、高精度に加工できるワイヤカットや放電加工は便利な加工法です。 ワイヤカットや放電加工のやり方以上に、割れや変形をさせないように熱処理しておくことも大切です。 熱処理後にワイヤカットや放電加工をする場合の注意点について紹介しています。
→このページへ
7 SUS304の溶接時に起きやすい問題と対策
SUS304などのステンレスを溶接すると、変形や着色で困ることがあります。 その対策は簡単ではありませんが、応力除去や着色部の対策や問題点などを紹介しています。
8 ステンレスの種類に対する熱処理の基礎
ステンレス鋼は大きく分けて3種類(すこし詳しくなると5種類)に分類されています。 鋼種も多く、鋼種名も特徴がないのでわかりにくいようです。 それらの分類や特徴とともに、それぞれの熱処理について簡単に説明しています。
9 熱処理の方法や考え方は変わってきていますか?
熱処理理論が確立した昭和年代後期と現状の熱処理について、一般鉄鋼熱処理における違いなどを紹介しています。 設備更新はあっても、熱処理の考え方の基本は変わっていないのですが、省エネ、省力化は進んでいるものの、考え方や作業の内容はそんなに大きく変わっていません。
10 機械構造用炭素鋼(SC材)のJISの熱処理
SC材の熱処理に関係するJIS規格(規格票)には、過去には、熱処理の方法や熱処理後の硬さや機械的性質があって便利でした。 その参考資料にあったデータは、今でも生きており、それらがJISで規定されているように思っている方も多いようです。
それらのデータは小さな試験片によるもので、少し大きな品物になると、そこにある結果と異なってきますが、まず、基本的なデータの見方を知ることが、SC材に限らず、機械構造用鋼の熱処理の基本ですので、データの見方などを説明しています。
11 機械構造用鋼の焼ならしについて
連続圧延設備を用いて製造された丸棒鋼(条鋼)は、特に、焼ならしをする必要がないのか?という疑問に対して、シミュレーションでの冷却速度とCCT曲線から組織硬さの状態をみて、硬さが適当であれば問題ない・・・という考え方を説明しています。
12 熱処理現場とSI単位系
鉄鋼の熱処理は1950年代ごろに確立されたものも多く、その資料が現在も生きているのでSI(国際単位系)化が遅れており、『℃x時間』という表現が主流です。単位についての雑学を紹介。
↑このページの上へ