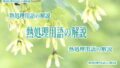「応力」とは、外力に対応する品物の、内部からの反力を指します。
そして、残留応力とは、その外力を除去しても残っている「応力」のことをいいます。
熱処理の焼入れは応力を高めるたのに行いますが、ここでは、品物に問題をもたらす応力について取り上げています。
熱処理での硬化は残留応力を付加していること
焼入れなどによって強度(硬さ)が増す … ということは、外力に対する抵抗力(つまり、応力)を高めることをして人為的にやっているということです。
強度を高める目的で熱処理をするので当然ですが、ここで取り上げる「熱処理の残留応力」は、残留応力が変形や破壊などに及ぼす「悪いもの」と言う面で取り上げられることが多いようです。
残留応力は、大きく分けて、引張応力と圧縮応力などとして作用します。
一般的には、品物の表面部分に圧縮応力が加わっている状態が良いとされます。
例えば、表面部分だけを硬化させる高周波焼入れは、表面が圧縮残留応力状態になるので、回転軸などでは疲労強度は極端に向上します。
これとは反対に、引張応力はいろいろな悪影響があります。
例えば、切り欠き部などに引張応力が集中すると、割れなどが起こるために良くない … などの説明をされます。
マクロ的な破壊は引張応力が原因
品物を焼入れして硬化すると体積膨張が起こることで、それによって応力が増加し、それが、品物の部位によって、引張力や圧縮力として働きます。
応力が均一に分布するような単純形状の品物では問題が起きることは少ないのですが、通常の品物の各所の形状や厚さなどが異なっているので、特定部分に引張力が集中する部分も出てきます。
その部分で、材料の持つ強度を上回ると、その部分から破壊する … とされます。
これはしばしば、形状的な応力や外力の集中によるマクロ的な破壊原因の例として説明されます。
熱処理で発生する脱炭は引張応力の原因に
焼入れ焼戻しで全体硬さが上昇すると、体積膨張して、全体的には圧縮応力が生じている状態になります。
しかし、複雑な形状では、応力の偏りが生じます。 また、隅や奥まった部分では引張応力状態になる部分が出てきます。
鉄鋼の機械試験を考えるとわかるのですが、引張試験では材料が破断しますが、圧縮試験では、試験片が砕けてしまうことは稀ですね。
つまり、品物の破壊は引っ張り力やせん断力が影響するのですが、このために、引っ張り力は破壊につながるという考え方になっています。
熱処理での脱炭は破損の原因の一つ
品物の表面に引っ張り応力が生じる例で、「熱処理中の脱炭」があります。
鋼は焼入れ硬化して部分は体積が膨張します。
しかし、熱処理中に品物の表面の鋼中の炭素分が失われるのが「脱炭」ですが、これが生じると、その部分の焼入れ硬化が不十分になり、その部分より内部が硬化するので、品物の表面に引張応力が生じます。
この部分が引張強さを超えると最終的には焼割れや使用中の破損が生じやすい … ということです。
小さな試料では応力を測定することもできますが
応力は硬さの変化などで測定されて示されることもあります。
その他には、結晶粒の歪の程度をX線で測定して、その大きさを残留応力値として数値で表わされることも多いようです。
ただ、品物の「割れ原因の調査」などで、破壊した後に品物を測定することもありますが、破壊によって応力の状態が変化してしまうので、破壊前の状態を知ることが難しく、また、破壊後の測定では、破壊が応力状態によるものかどうかを特定することも簡単ではありません。
だから、経験的にそれを判断することも多いのですが、基本的には、引張応力を集中させない工夫について、常に意識しておくのがいいでしょう。
しばしば、焼入れでは隅部の冷却が遅いので「その隅部から割れる … 」などと言われることがありますが、これは眉唾ものです。
通常は、冷却が遅いと、硬さが十分入っていないので、伸びや絞り値が高いので、そこから割れることはありません。
割れるのは、引張応力の集中部ということで考えるのが妥当です。
それはともかく、破壊の原因になる残留応力の集中を緩和するために、「鋭角部をなくす」「隅角部はRをつけてなめらかにする」… などの一般的な対策は、つねに考えておく必要があります。