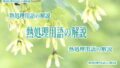鉄鋼の熱処理品の硬さについては、手に持てる程度の金型や製品は、ここで紹介するロックウェル硬さ試験機を用いて測定する場合が多いです。
JISにはロックウェル硬さ以外に、ブリネル硬さ、ビッカース硬さ、ショアー硬さなどについての規定があります。
ロックウェル硬さ計には、硬さ単位の異なるC・A・Bなどのスケールがあって、それぞれ測定方法がJISなどで決められています。
このうち、鉄鋼の硬さ測定では、比較的、Cスケールを用いたHRC硬さがよく用いられます。
また、Aスケールは、押し込み荷重を小さくしたもので、大きな圧痕をつけたくない場合や、高い硬さの測定に用いられます。
また、Bスケールはやわらかい品物を測定する場合に用いられます。
硬さの特殊性
硬さ値は「指標のようなもの」で、単なる数字で、試験機や試験条件が違えば変わります。
そこでJISには、試験機、硬さ基準片、測定方法についての規定をして、硬さの正確性をたもっています。
JISでは試験機自体や測定方法の規定がありますが、実際の熱処理品などを測る場合の詳細な規定などはなく、品物に応じた試験は、作業者(検査者)の技量によってその正確性が保たれているところが大です。
そして、JISでは硬さ換算表の規定もありません。(アメリカの規格の換算表がJISハンドブックなどに掲載されています)
注意する点では、熱処理品の検査では、品物の安定した平面部分など、測定部位が限定される点と、さらに、表面硬さ以外の測定は普通は行われません。
このような特殊性があることも知っておくのがいいでしょう。
硬さ換算表について
測定するスケールが違えば、硬さ値間の相互関係はありません。
しかし、それでは不便なので、アメリカのSAE・ASM・ASTMなどの機関が調整した「硬さ換算表」が広く用いられており、その不便さを補完しています。
硬さ換算表を利用すると便利ですし、それを利用した換算値でトラブルになることもありません。
もっとも、使用するのに不都合があるようなら使わなければいいのですが、それを細かく取り決めようとすると、かなりの知識が必要になるので、相互の信頼で暗黙的に使われている感じもあります。
硬さ換算表は、あくまでも簡便的なことで使用されているものであることを知っておく必要があります。
試験値の読み方
ロックウェルCスケールで測定した硬さは、 ①「ろっくうぇる・しー・かたさ」 ②「エイチ・アール・シー・かたさ」などと称されます。
 ロックウェル硬さ測定
ロックウェル硬さ測定
硬さの表記は 60HRC のように書きます。
これは普通は、「えっちあーるしー60」 といいます。つまり、ロックウェル硬さ試験機のCスケールで測定した値が60 … だということです。
この硬さは、指定のダイヤモンド圧子を使って、与圧をかけたあと、150kgで押し込んだ時の押し込み深さで硬さを算出します。
硬さ値はゲージに表示された数字を読み取ります。 近年は、デジタル表示の試験機が増えています。
品物の硬さが高いほど、荷重をかけてダイヤモンド圧子を侵入させにくいので、その侵入しにくさを数値で表示しています。
この数字が大きいほど「かたい」ということです。
鉄鋼では、焼なましした品物ではゼロ以下のマイナス数字が出るので、その場合は、Bスケールでの試験をするか、ブリネル試験機などの、その他の試験機を用います。
このロックウェル硬さ試験機は精密なものですが再現性が高く、測定値のばらつきも少ないので、鉄鋼の焼入焼戻し品の硬さ検査では多用されています。