硬さ基準片は熱処理の品質を支える [k15]
熱処理における硬さ試験は熱処理品の品質を決定するために重要なものです。
その硬さ試験機の精度保持のために作られたものが「硬さ基準片」です。 「テストピース」と呼称されることもありますが、JISでは、「硬さ基準片」といいます。
これもあって、JISの要求精度などの基準を満たしていないものは、硬さ基準片とは呼ぶことはできません。
国内で使われている硬さ基準片の多くは「旭工業所」製か「山本化学工具研究社」製のものが使用されています。
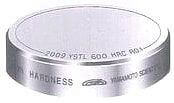 (株)山本科学工具研究社のロックウェル硬さ基準片
(株)山本科学工具研究社のロックウェル硬さ基準片
硬さ基準片は硬さ試験機の管理や校正に用いられるもので、JISでその仕様が規定されています。
そのため、硬さ基準片の硬さ値は厳格に管理されていることもあって、高価になってしまうのは仕方がないかもしれませんが、日を追うごとに価格が上昇するので、私の勤務した第一鋼業では、一時期には、自社で硬さ基準片を自作していたこともあります。
しかし、自社管理となると、管理も大変で、思ったほど安価に製作できなくなって、仕方なく、毎年、かなりの数の硬さ基準片を購入しているのが実情です。
熱処理現場では、定期的な管理のためだけではなく、日常作業での使用頻度も高いのですが、高価なことで、簡便には使いにくい … という問題もあります。
PR硬さは熱処理品質を決める大切なもの
硬さは、引張強さなどの機械試験値に替えるものとして最重要な指標ですので、硬さ試験機の精度維持には、この硬さ基準片が必須です。
つまり、JISの規定に沿った硬さ試験機と硬さ基準片によって「社内の硬さ値」が管理され、それによって熱処理後の製品の品質が保証されている … という仕組みで硬さの精度(硬さ値)が保たれています。(これを「トレーサビリティーが確立されている」という言い方をします)
このように、各社がそれぞれ「JISに基づいた硬さ」を管理しているのですが、(大変不思議なことですが) 各社ごとの硬さ値の違いや、購入した硬さ基準片の値がおかしい … ということを経験することがあります。
もちろん、硬さを管理している2社間の取引では、それぞれの会社が、お互いに自社で硬さの管理をしていますから、例えば、出荷検査の硬さと受入検査の硬さ値が違う場合には、硬さ値の相互調整をしなくてはならない … というおかしい状況もでてきます。
またさらに、新品で購入した「硬さ基準片の値」が当社の基準に合わないことも多々ありますし、基準片の製造メーカーが違うとその硬さの違いがあることも経験します。
この場合は、社内規定に沿って、硬さ基準片の硬さ値を社内の硬さに書き換えることもしますし、これで、自社の硬さ標準が変わっていくということにもなるのですが、それは「測定値」であるので、仕方のないことといえるでしょう。
これも不思議な事ですし、運用にも難しい問題を含みますが、硬さ基準片の製造会社でもJISに基づいた「値付け(硬さ値の確定)」をルールに基づいて値付をしているだけのことですから、現実的にはこのようなことは生じるのは仕方がないことです。
購入した新品の「硬さ基準片」は『硬さの標準値』であるというものではなく、「JISの規定に沿って値付けされたもの」というだけのものですから、基準にはなりますが、絶対ではないと考えて使う場合もあるのですが、硬さのばらつきなど、その他もJISに基づいて作られているので、ともかく、社内の硬さ基準にすることは何の問題もありません。
こういう微妙な問題もありますが、JISやISOの認証工場では、硬さに関するトレーサビリティー(国家標準の硬さ値につながる管理体系)が求められていることもあって、それに沿って「硬さ」は管理をされていますので、現状では、熱処理検査を含む硬さ値の精度に関するトラブルはほとんどありません。
ただ、実際の品物を検査するのと、硬さ基準片の硬さを測るのとでは状態が違いますので、硬さの標準を管理することと、品物の硬さを保証することとは別です。
例えばロックウェル硬さ試験機であれば、10kgf(重さ10kg)以上のものは測ってはいけない事になっていても、熱処理品となれば、それらを測定しないといけない場合もありますし、熱処理肌の品物を測定するなどのために、様々な誤差の要素が加わります。もちろんこうなると、硬さ基準片の硬さとは乖離してきます。
そのために、品物の硬さを保証するためには、試験機の管理とともに、硬さに対する技術、測定者の技能・能力なども重要になります。
(来歴)H30.12 見直し R2.4CSS変更 R7.8月見直し













